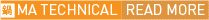作品づくりにおいて「MA」が担う部分、それは「音の編集」「音の演出」そして「音の仕上げ」。またそれは、作品づくりにおけるプロダクションワークフローの最終工程でもあり、作品の最終完成形を見られる唯一のパートでもあります。
そもそもMAとは、「Multi_Audio」の略。この名称は和製英語で、かつて音処理をするために開発された複数の音声トラックを持つ専用VTR、「Multi Audio VTR」を使用していたことから、そう呼ばれるようになりました。一部では音の最終作業ということから「Master Audio」という呼び方をしているところもあります。ちなみに英語圏では「Audio Sweetning」(オーディオスイートニング)と呼ばれています。
番組をはじめ、映画・ミュージックビデオなどの映像作品には様々な「音」が存在します。映像と同時に収録される音(同録)、後から加えられる効果音・音楽やナレーションなど、作品に関する全ての「音」が素材として「MA」に集まってきます。
作品の意図をくみ取り、演出上必要な音の選択、タイミングの修正や加工、「音」を磨き、様々な技巧と感性をもって混ぜ合わせていくことで、作品に命を吹き込んでいきます。
音は空気の振動によって伝わります。よって作品が静止していては耳に届きません。ゆえにミキシング作業はいわばリアルタイムのライブ演奏のようなもの。その演奏に向けたミックスイメージ構築と緻密な準備が、より良いミキシングの鍵となるのです。
映像に対し従属的なイメージのある「音」ですが、実は、映像と相まって作品を大きく昇華させる重要なファクター。その音をつかさどるMAは、「ミキサーによって作品印象が変わる」と言われるほど、個人の感性と技量が大きく反映される仕事なのです。そういった意味で、我々はエンジニアリングにとどまらず、テクニカルアーティストの素養を持ち合わせていなくてはなりません。
それでは、MAの一般的なフローをひもときながら、ミックスイメージ構築とその具象化に向けたいくつかのポイントをご紹介いたします。

編集から上がってきた映像素材をMA用のワークステーションに取り込む作業。MA作業は、音の編集作業や加工、音を加えてミックスする作業のため、それらに適したプラットフォームに素材を移行するのです。この作業は、一見単なるコピーに見えますが、映像をプレビューしながら取り込むことによって、音の状態や配置、トラック割りなどをチェックしたり、作品趣旨をくみとりミックスイメージの礎を作る大事な作業でもあります。
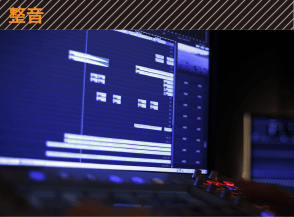
映像と共に収録された音声(同録)は、収録場所や収録機材、セッティングなどによって音量や音質が違い、時として非常に厳しい収録状態になっている場合があります。これらの素材を使用した編集上がりの映像は、演出上たくさんのカットが積み重なって構成されており、同じくくりとして処理したいシーンでも、カットごとに音の段差が生まれ、そのため自然なシーンとして見ることできなくなってしまう場合があります。また作品の内容に関係のない話し声やノイズなど演出上好ましくない不必要な音も入ってしまっていることもあります。
「整音」では、これら音声の音量調整・音質補正を行い、音を聞きやすく、より作品に入り込みやすくしていきます。演出上必要な音と不必要な音の判断をし、必要であれば音声の差し替えなども行います。
また作品にメリハリをつけるために様々な音の演出もしていきます。
リアル感を増すために、歩きながらの会話や車の走行・アップ・ルーズなどに合わせて音量や音質で遠近感をつける、電話や拡声器を通しているような加工、空間演出のためのエコー処理などもこの段階で行います。
そのほか、爆発音などをより引き立たせるためその直前の音を一瞬なくす、はっとするような心情的なシーンでノイズをあえて消す、言葉を引き立たせるため言葉尻であえてノンモン(無音)にする、など様々な手法も用います。
このように整音作業は、単なる音のならし処理ではなく、作品の内容をくみ取った「構成力」が問われます。その音を活かすのか消すのか。作品内容を踏まえ最終仕上がりをイメージしながら音を組み立てていきます。音の構成によって作品の印象は大きく変わります。すでにこの段階から最終的なミックスイメージを意識し作業をしているわけです。

作品の「音」を語る上で欠かせない要素が「音楽」。
昨今の作品において音楽のもたらす効果は絶大で、なくてはならないものとなっています。音楽をつけることによって、シーンを一連のくくりに見せる、時間経過を表現するなどの効果のほか、テーマや演出上の意図を感じさせたり、感情に訴えかけたり、シーンの演出効果をより増大させたりすることができます。
映像につける音楽の種類は、作品のジャンル・手法によって様々考えられますが、主観的な部分が多いため、選曲マンによって曲の選び方は十人十色です。悲しいシーンに悲しい曲をつけるのではなく、あえて明るい曲調にすることでより悲しさが引き立つ、などの表現があることも事実です。それらが積み重なることによって作品の「色」となっていきます。一方、報道番組などは事実報道に「色」 をつけないように、無味無臭な曲(業界では淡々系と言ったりしますが)をつけ、視聴者に主観的なイメージを押しつけない配慮もしています。内容を鑑み、あえて曲をつけないという選択も立派な「選曲」と位置づけられています。
音楽の種類・曲調はもちろん重要ですが、無視できないのが曲のイン・アウトのタイミング、映像とフレーズの同期や呼応です。これらが視聴者の呼吸、映像にマッチした時、効果は爆発的に増大します。心にすっと入ってくる、作品にのめり込める、琴線に触れるような演出をしたい場合、この音の「タイミング」にも気を配る必要があります。
音の構成をしていく上でもう一つ必要なもの、それは「効果音」。
効果音には色々な役割があります。シーンをよりリアルにするためにつけるもの、現実にはない音だけれどもテロップや被写体の動きにつけることで、シーンをより滑稽にしたり、スピード感を出したり、重々しくしたり、などの「効果」をもたらすもの、があります。
私たちは音を「主観的」にとらえていることが多々あります。たとえば雨。私たちが普段聞き慣れている、またはイメージしている雨の音と、実際マイクロフォンを通して記録された雨音を聴き比べてみると、ずいぶんイメージが違うことに気がつくことがあります。また自分の声を録音して聴いてみると、いつもと違う声に聞こえる経験したことがあると思います。これらには様々な要因がありますが、人間は耳から入ってくる音を、様々な他感覚や情報でフィルタリングし、脳で処理して聴いているという事に起因しています。現場にいて聴いている時と、それを録音して聴くのとでは状況が違うため、脳で処理して聴く音も違って感じるのです。忠実に録再すれば、その場を再現できるとは限らないのです。
我々はその事を踏まえ、より作品に違和感なく入っていけるように、主観的な音作りをする場合があります。たとえば何気ない「街中の会話」。現実では会話が成立しないほどうるさく感じることはあまりないと思いますが、同じ場所で録音した会話をあとで聴くと、周りの音にマスキングされうまく聞き取れない場合があります。これは脳が視覚を含めた様々な周辺情報を統合処理し、聴くべき音に集中しているからで、カクテルパーティー効果と呼ばれています。我々は、収録現場と違う作品の視聴環境において、それらを加味した音作りをすることで、一見リアルではないが、よりリアルに感じる音演出をしているのです。
たとえば、街中の雑踏の中で彼女に「別れよう」と実際言われたらどう感じるか。その言葉だけが響き、周りの音などは聞こえないかもしれません。
目前で人が車にはねられそうな状況を目の当たりにしたら、血の気がひいて一瞬周りの音が聞こえず、スローモーションのように感じることがあるかもしれません。
このような人間が脳で感じる主観的な知覚が「リアル」であり、作品によってはそのようなことを想定しながら、音演出をしていきます。
この技法は、このようなアクティブな音演出のみならず、たとえば遠くにいるときにはより遠く、近くにいるときにはより近く感じるような音量・音質調整をするなど、自然なシーン作りにも生かされています。
このように、音楽・効果音・技法を一つ一つ積み重ねていくことで、映像は作品へと昇華していきます。
音楽と効果音の素材を準備しMAに持ち込むのは「音響効果」(略して音効)と呼ばれる音付けのプロです。MAミキサーは音響効果とコラボレーションしながら、同録と後付した音素材が作品上で違和感がないよう、さらに調整作業・ブラッシュアップをしていきます。
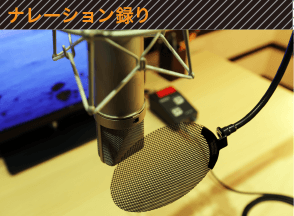
情報を伝える側面を持った作品において、ナレーションが入っているものが大半を占めています。映像だけではなく、「言葉」によって、作品をより深く理解し、感じてもらうためです。そのため、ナレーションの「てにをは」「ですます調か否か」「イントネーション」のチェックのみならず、視聴者に一番近いより客観的なMAのポジションを生かし、「理解しやすいわかりやすい文章」などの提案を行う場合もあります。
映像にナレーションが入ることによって、作品の趣旨、映像の意味、登場人物の心境、時系列の変化と、あらゆるものが明確になっていきます。またナレーションの声質・トーン(激しく読む、淡々と読む、おもしろく読む)などで、作品のテイストを印象づけるという役割もあります。ナレーターを誰にするのか、男性にするか、女性にするか、ナレーターの過去の作品履歴や社会的立場も、作品イメージを形作る上で重要なポイントです。多くの場合、ナレーターを誰にするかは演出サイドが決めますが、音効やミキサーの音響チームにアドバイスを求めたり、場合によっては音響チームがナレーターを決めることもあります。
プロのナレーターのみならず、作品の内容によっては、俳優や歌手、スポーツ選手や声優が担うこともあります。ナレーションの経験がない人でも、作品がその「テイスト」を求めるのであれば採用することもあります。上手下手ではなく、語りの味が作品に深く入り込ませてくれることもあるでしょう。正に「声による演技」がそこでは行われているのです。
ナレーションにおいても、音楽や効果音と同様に「タイミング」=「間合い」は重要となります。言葉と言葉との「間合い」、映像とのタイミング、その映像が生きるか否か、この「間合い」が肝となります。そのタイミングの調整を行う「ナレーションの上げ下げ」を、「言葉」の風合いをこわさないよう注意を払いながら行います。場合によっては「言葉」に合わせて音楽や効果音をずらす場合もあります。信じられないかもしれませんが、見る人の呼吸を感じたこれらの「間合い」の調整によって、そのシーンが持つ持たない、映像が生きる生きない、作品への理解度・没入度が決まると言っても、決して言いすぎではないでしょう。
作品は数多くの音素材で構成されていますが、インタビューやセリフ・ナレーションなどの「言葉」は、多くの場面で作品の「軸」となるもの。ミキシングで個々の音のバランスを決めていく際にも、「言葉」を軸に組み立てが行われていきます。
ナレーション録りのタイミングで、その他の音素材の仕込みが終わっていた場合、ナレーションを録りながら、並行してミキシングの当たりをつける作業を行います。「言葉」が「軸」ですから、それにあわせた音楽のフレーズ・同録や効果音のバランスを確認しながら、ミキシングイメージを具象化しチェックしていくわけです。ミキシングの本番で、演出陣を背にリアルタイムにミキシングを行っていくということは、ライブで観客を前に生演奏するようなもの。ナレーション録りと並行して行うミキシングチェックが、現状唯一のミックスの練習の場となります。ナレ録りをしながらバランスチェックが出来るのか、チェックせず一発本番となるのか。意外と軽視されている作業かもしれませんが、ミキシングクオリティーにも大きく影響する重要なポイントなのです。

ミキシングにおいて、ミックスイメージの具象化というクリエイティブ面は当然ですが、それ以外に気をつける点があります。納品するにあたって、必要なルール、技術規格、納品基準に作品が沿っていなければいけないという点です。基準にあっていなければ、どんなに良いミックスであっても、納品出来できなくなってしまいます。また本編の他に、データや整音済みのバラ素材(ステム)など副次的に納品しなければならない場合もあります。音の最終工程としてだけでなく、プロダクションでの最終作業・最終チェックを担うポジションであるということも意識し、作品内容は問題ないか、納品基準に沿っているか、過不足はないかなど、作品の管理もしなくてはいけません。
「ラウドネス納品基準」は、視聴者のホスピタリティを考慮し、作品間の聴感レベルのばらつきを少なくするための基準として導入されましたが、技術面を含め十分な理解をした上で、ミキシングを行います。「ラウドネス納品基準」は、作品の音量感を-24LKFSという基準に合わせるというもの。「言葉」が作品の「軸」ということから、「言葉」の平均レベルが-24LKFSを超えない程度とし、そこを基準に他の音素材のバランスを決めていけば、多くの場合は基準内に収まります。これら表現とは別の次元の知識やテクニックも、ミキシングエンジニアには不可欠です。
MA最大の山場、要となるミキシング。
MA作業で行ってきた様々な作業、「整音」「音加工」「効果音・音楽付け」、「ナレーション収録」、そしてそれぞれの音素材の「タイミング調整」、これら全ては、最終的にに音をまとめ上げるミキシング作業をよりスムーズに、より良くするために行う作業です。これらの作業を調理にたとえるならば、材料を洗ったり切ったり下ごしらえするようなもの。そして音をまとめ上げるミキシング作業はまさに料理。MAで行う全ての作業は、この「ミキシング」によって完結します。
ミキシングエンジニアにとってまさにミックス作業こそが醍醐味であり、一番神経を使う所です。フェーダーを操りそのシーンに最もふさわしいと思われるバランスを見極め、全ての音素材を操りながら、リアルタイムに作品の「音」を演奏していきます。音楽家が楽器や声で自らの世界感を表現するように、ミキサーはミキシングで作品の世界感を表現していきます。一つ一つの点であった音素材が、ミキシングによって多彩な面へと姿を変え、映像と合わさり呼応することで、奥行きのある生きた作品に昇華していく。その様を具体的にからだで感じとれる、最高の瞬間でもあります。
このようなプロセスを経て、作品は完成します。
しかしこれらはMA作業のほんの一端です。作品ジャンル別に様々なテクニックが存在しますし、音楽ミックス、映画やサラウンドなど、さらなる知識や経験が必要とされるものもあります。MAという作業は、この場では書ききれないほど、幅広く、奥深く、そして面白さに満ちたものです。
「音」、耳を傾けると、作品の中にはじつに様々な音が存在している。その音ひとつひとつが、絶妙なバランスで、作品をリアルに響かせる。そのことによって、作品の訴求力・感動レベルを増大させ、見る人の心に何か響かせる。その影には、テクニカルアーティストである私たちミキシングエンジニアの地道な努力が、あるのです。
「作品を見た人が何とも言えない読後感を感じた」
我々がそう確信したとき、普通の仕事とはひと味違う「この仕事の意義」を感じるのです。